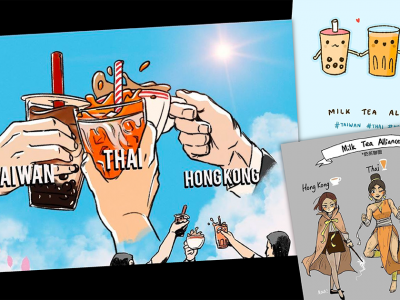ユセフ・ナビル作「Self-portrait」エッサウィラ 2011年 手彩色を施したゼラチン・シルバープリント (courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels)
イタリア、ヴェネツィアにあるパラッツォ・グラッシ美術館は、有名なエジブト人アーティスト、ユセフ・ナビルによる120枚の写真と3本のフィルムを展示する「Once Upon a Dream」を2021年1月10日(訳注:パラッツォ・グラッシ美術館WEBサイトによれば、2021年3月20日までと記載されている)まで開催。この展覧会でキュレーターを務めるマチュー・ヒューメリとジャン=ジャックス・エラゴンは、「ユセフ・ナビルの軌跡をたどる120枚以上の作品」を選んだ。
1972年にエジプトで生まれたナビルは、今や世界を代表する写真家、アーティストの一人だ。彼の作品は、この10年間、世界中の展覧会や美術館で注目を集めてきた。ナビルはモノクロ写真に彩色を施すことで、被写体を写真では到達しえない構図に完成させた。1940年代から1950年代の手描きの映画ポスターに触発され生まれた彼の手法は、ペインティングと写真を組み合わせたもので、デジタル化以前の世界を彷彿させる。
ナビルの写真は、ノスタルジアと理想主義、脱構築と美、現実と幻想の融合であり、つまるところ、作品を作り上げる中で行われた繊細な介入による産物である。彼の作品を形成する過程において、彩色を施すことは写真を撮ることと同じくらい重要な意味を持つ。彼は、「私の写真は、それぞれに違う被写体と自身の個人的なつながりから生まれたものであり、その異なる関係性から、最終的にはそれぞれがすべて異なるものとなる」と語っている。
やがてナビルは映画製作へ歩を向ける。彼はGVとのインタビューで、映画という新たな創作素材を用いた芸術表現について、写真、そして自身とエジプトの関係について語っている。
以下、インタビューより抜粋。

ユセフ・ナビル、2020年9月 イタリア・ヴェネツィアのパラッツォ・グラッシ美術館で開催された個展にて(Photo courtesy of the artist, ©Matteo De Fina)
オミッド・メマリアン(以下OM):あなたはとりわけ写真と人物画でよく知られていますね。また、3本の映画「You Never Left」(2010)「I Saved My Belly Dancer」(2015)「Arabian Happy Ending」(2016)を製作されました。あなたにとって、映画という表現手段は、写真では得ることができない何かを与えてくれるものなのでしょうか?
ユセフ・ナビル(以下YN):私は、写真表現をしている時はいつでも、心の中で映画を作っています。まるで物語を語るかのように準備を進め、細部まで気を配ります。写真を映画のワンシーンのように感じてもらいたいと思っています。言わば私にとって映画は、写真表現にインスピレーションを与えるものであり、そもそも写真を撮り始めた理由そのものなのです。技術的にも、写真に彩色を施す私の手法は、映画制作法や古い手描きの映画ポスター、映画スターの肖像画、そしてテクニカラー映画から取り入れたものです。あのヴィンテージ感を、現代的なアプローチで写真に取り入れたかったのです。カラーフィルムは使いたくありませんでした。デジタル時代を迎える前の話です。90年代初頭、誰もがカラーフィルムを使っていましたが、それでも私はモノクロで撮影し、それまでと同じ古い写真技術を使って彩色を施したいと思っていました。したがって、写真から映画への移行は自然な流れでした。今は長編映画の製作を考えているところです。

ユセフ・ナビル作「Marina Abramović」ニューヨーク 2011年 手彩色を施したゼラチン・シルバープリント(courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels)
OM:肖像写真を始めたきっかけは?
YN:自分が会いたいと願った人々、つまりテレビや映画館で見て育った数々の象徴的な人物、俳優や女優たちです。私はただひたすら彼らに会いたかったんです。なぜなら、「時」に関する重大な事実に気がついたからです。わたし達より前に生きたもしくは後に生きる人々にも平等に死という瞬間が訪れる、という事実です。私は幼くしてこのことに気づきました。そして私にとってカメラは、一瞬の「時」を止めて永遠にすることができるおそらく唯一の表現方法でした。彼らが俳優や友人、家族、あるいは自分自身であろうと、私にとって、写真とはめぐり逢い、出会い、いつか出会うかもしれない人々との一瞬を捉えるものなのです。残るものが何であれ、作品は、私たちが出会ったという証なのです。
OM:あなたはエジプトで育ち、2003年にアーティスト・イン・レジテンス(訳注:招聘されたアーティストが、特定の土地に滞在し作品の制作やリサーチ活動を行なうこと、またそれらの活動を支援する制度を指す)としてパリに移り住みました。その後、2006年から2018年まではニューヨークで過ごされています。これまで過ごされてきた環境はあなたの作品(特に独創的な手彩色の肖像画)にどういった影響を与えているのでしょうか?
YN:技術面にしても題材にしても、これまでの作品はすべて私の個人的な経験から着想を得ています。写真に彩色を施すというインスピレーションを私に与えてくれたのはエジブトです。子供の頃、家族が運転する車の後部座席によく乗っていたのですが、道すがらに飾られた映画の看板を見つけては眺めるのが私のお気に入りでした。カイロは「ナイル川のハリウッド」とも呼ばれるほど映画の盛んな都市で、街のいたるところにある手描きの映画ポスターを見て私は育ちました。エジブトの家では手描きの家族肖像画もたくさん飾られていました。そういったものを自分の作品に取り入れたいと思ったのです。それはまさに、エジブトで触れた体験や暮らしに根ざした思いです。
私はアートや映画を学びたかったのですが、2年間、エジプトの美術学校はすべて不合格に終わりました。悩んだ末、自分で創作を始めることに決め、学生時代の友人を呼び出してカメラを借りたんです。そしてその数年後に、友人を被写体として撮ったモノクロ写真に彩色を施したいと思うようになりました。私は昔の映画からインスピレーションを得て、カラーフィルムは使わずに、モノクロ写真に彩色を施す手法を学びました。そのためには、唯一残っていた古いスタジオ「レタッチャー」から技術を学ばなければなりませんでした。自分の作品を絵画のように見せたかったのです。写真と絵画の組み合わせがとても好きでした。もちろん、エジプトからニューヨークへ移っても、そんな気持ちが変わることはありませんでした。それはとても自然なことで、作風を変えないように決めていたわけではありません。

ユセフ・ナビル作「Self-portrait With Roots」ロサンゼルス 2008年 手彩色を施したゼラチン・シルバープリント(courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels)
OM:写真に使う色はどのように決めるのですか?
YN:自分の好みや自然と湧き起こる感覚を頼りに決めています。ある色味の青が好きで、作品にもよく使っているので、今では多くの人がその色を見て私の作品だとわかるようになりました。同様に、肌の色や赤色についても、好きでよく使っているものがあります。私にとって、すべての決定はとても個人的なことです。
OM:あなたが製作された3本の映画はすべて、困難を抱える地域を舞台に現代の社会問題を扱っています。セクシュアリティに始まり、「エジプトへの別れと郷愁」についての自己探求、そして自由まで。あなたが作品の中でこういった問題を提起したことに対して、アートの世界からはどういった反響がありましたか?現在の写真表現にも影響を与えていますか?
YN:個人的な感情や経験、懸念、そして自分の礎をなす文化について触れる時にはいつも、私はそういったものを普遍的なレベルへ昇華させようとします。誰もが共感できるようにです。「I Saved My Belly Dancer」では、ベリーダンスが不道徳だという理由で中東の一部の人々から繰り返し間接的な攻撃を受けていることに言及しました。この映画はどちらかというと、たとえ現実から失われてしまっても記憶に残して人生をともにしたいと願うものを主題としています。私の場合、それがベリーダンサーだったわけです。人によっては、もう傍にはいない愛する人かもしれませんし、移り住む地として選んだ国にはない、生まれ故郷で得た幼少期の思い出かもしれません。したがって、私にとって、この映画のテーマは「記憶」なのです。「You Never Left」では、故郷を離れ別の場所へ移ったとしても、生まれ故郷はずっと心の中にあるということがテーマです。私自身、自分の中で小さな死が起こっているのを感じ、新たな地で生まれ変わらなければなりませんでした。別の地に移り住む人なら誰でも、こういった感覚に共感を覚えると思います。

ユセフ・ナビル作「Your Life Was Just A Dream」2019年 手彩色を施したゼラチン・シルバープリント(courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels)
OM:あなたの写真を眺めていると、どういうわけか時間や現実性の要素が取り払われ、自分の記憶の中にある独創的な空間に連れていかれるような感覚を覚えます。このような特性を生み出す、思考プロセスとはどのようなものなのでしょうか?
YN:決して、意図的に行っているわけではありません。自分自身、自分の性格や人生、他人を見る目、自己表現のやり方、メッセージをどのように感じ捉えてもらいたいのか、などといったものであり、それこそ言葉にできないものから生まれています。だから私は写真を撮ります。それこそが、私が共有したい世界観です。意図的に人を笑わせたりしないのも、自分の後ろ姿を写真に撮るのも、それが理由かもしれません。そうしようと決めているわけではありません。絵について言えば、どのタイミングで作品は完成すると思いますか?自分が完成したと言えばそれはもう完成なのです。ですから私は何かを決める時はいつも、流れに身を委ねて、自分の感覚を頼りにするのです。

ユセフ・ナビル作「Catherine Deneuve」パリ 2010年 手彩色を施したゼラチン・シルバープリント(courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/ Brussels)
OM:あなたの作品に最も影響を与えているアーティストは誰ですか? また、そういったアーティストから得た芸術的体験や芸術の捉え方とはどういったものですか?
YN:私のビジョンを形作ったのは間違いなく映画です。それも古い、エジプトやヨーロッパ、アメリカの映画です。80年代のカイロで私は育ちましたが、当時はまだインターネットやケーブルテレビ、携帯電話がありませんでした。その後、アンディ・ウォーホルやジャン=ミシェル・バスキア、キース・ヘリングなど、特にニューヨークで活躍する様々なアーティストの存在を知りました。当時の私は、80年代アメリカの芸術運動について非常に興味を覚えていました。特に興味を抱いたのはアンディ・ウォーホルですが、彼に、大きく影響を受けたわけではありません。90年代、私はニューヨークへ行き、さらに多くのアーティストを知りました。そのうちの一人がフリーダ・カーロです。1993年3月、彼女の初の伝記本が出版され、私はニューヨークでその本を読みました。フリーダ・カーロは主に自身が抱える痛みをアートへと昇華させていて、私はそんな彼女の生き方に触発され、感動し、魅了されました。彼女はただひたすら自分の人生をアートにしていました。ジャン=ミシェル・バスキア、大好きなアーティストです。創作素材やアートの類に関係なく、自分の人生を作品に傾けているアーティストが私は好きです。作品に込められたアーティストの内面をただただ感じたいのです。
パラッツォ・グラッシおよびプンタ・デラ・ドガーナはピノーコレクションによる現代美術館で、イタリア・ヴェネツィアに位置する。